重松 清 インタビュー
映画化のオファーをどのように受けとめましたか?
「ステップ」に関しては映像化のオファーはないだろうと思っていたんです。10年に渡るタイムスパンのある話なので、子供を含めたその間の成長を実写で撮るのは難しいだろうなと。でも飯塚監督から直接手紙をいただいて、映画化への思いを受け取って、この作品を預けてみようかと思いました。僕はもともと飯塚監督の「荒川アンダー ザ ブリッジ」が好きで、ひそかに健一を山田孝之さんが演じてくれたらいいなと思っていたのですが、それが叶ったときは「やった!」と思いましたね。
小説も映画も妻の死から1年後にスタートしますが、執筆時はどんな思いを込めて書かれたのでしょうか。
「はじまり」の物語を書きたかったんです。死を悼むことも大切だけれど、そろそろ前も向かなきゃいけないというタイミングで、悲しむだけの話にはしたくなかった。とはいえ失った相手の存在が完全に消えるわけではないので、無理に消そうとすると無理が出てくる。誰かの「不在」という存在を引き受けながら、それと共に生きていこうとしている人たちの姿を描きたいという思いがありました。
山田さん演じる健一の、亡き妻への向き合い方をどうご覧になりましたか?
妻に先立たれた後の健一には、別の女性を好きになったり、自分が幸せになることに、微妙な後ろめたさみたいなものがあると思うんです。亡くなった妻に対しては新しい恋や関係を始めることへの申し訳なさ、新しい妻に対しては前の妻を忘れ去ることができないという申し訳なさがあって、その二重の申し訳なさが山田さんの表情の一つ一つに出ていたし、広末涼子さんのお芝居にも表れていたのが素晴らしかった。僕は自分の小説でも葛藤の間で揺れている人間を描くのが一番好きなんです。
それぞれが葛藤した分だけ成長につながっていく。
そう。これがたとえば亡き妻の父親である明の目線だったら、もし健一と結婚していなければ、娘は早逝しなくて済んだかもしれない……という思いが心をよぎることもあったと思うんです。一緒にいながらどうして娘の異変に気づかなかったのか!? と言いたくもなったはず。でもその思いを飲み込みながら、親父として健一に接する國村 隼さんの明は、さすがに器が大きいねという貫禄を出してくれた。作家として、明の気持ちを新たに書いてみたいという欲求が芽生えるぐらいの名演でした。葛藤を解決するのではなく、共に生きていくために、器や度量を広げるのが大人の成長だと思うんです。子供の成長は縦に伸びていくものですが、大人の成長は横に広がるんですよね。
誰の立場に立つかによって、見方の変わる作品でもありますね。
僕自身も連載当時は44歳ぐらいで、健一の目線に近かったのですが、そこから歳をとるにつれてだんだん明の目線に移っているんです。観る人の年齢や家族環境、そのときの状況によって視点を変えながら、読者が長くつき合っていける小説を書きたいと思っているので、この映画はその理想と同じような愛され方ができる作品になったと思う!節目節目で健一と美紀が渡る鉄橋の道、健一が上司と昼食を食べるお約束のリフレイン、地道に巻き寿司の練習をするシーンもよかったですね。そうした一つ一つの場面を積み重ねながら一段ずつステップを踏んでいく。人生にジャンプはないんです。
映画化を経た今、「ステップ」はご自身にとってどんな一作になりましたか?
10年の年月を2時間で描くということは、描かれない隙間がたくさんできるということでもあって、その余白からさらに想像が広がっていく。のこされた人の数だけ物語があるんですよね。エンドロールの後も、出てきた人たちが生きていると感じられて、その先をまた書きたいと思った。家族って、決してまん丸な満月ではないと思うんです。みんなちょっとずつ何かが欠けていたり、足りなかったり、失われていたり、思い通りにならなかったりするけれど、それを補ってくれる誰かがいる。そのことを信じていいんだと教えてくれるベースキャンプが、親子や夫婦だと思うんです。映画『ステップ』は、原作の思いをさらにパワーアップさせて、次にこの物語を必要としている人に手渡すバトンになってくれたと思います。












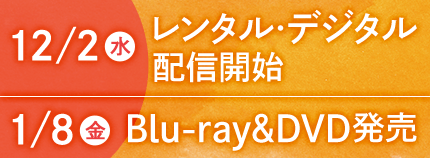

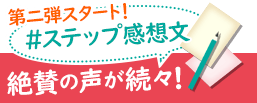


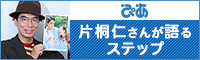

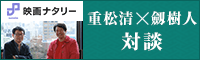











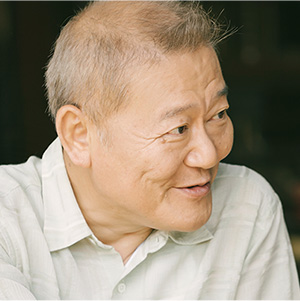







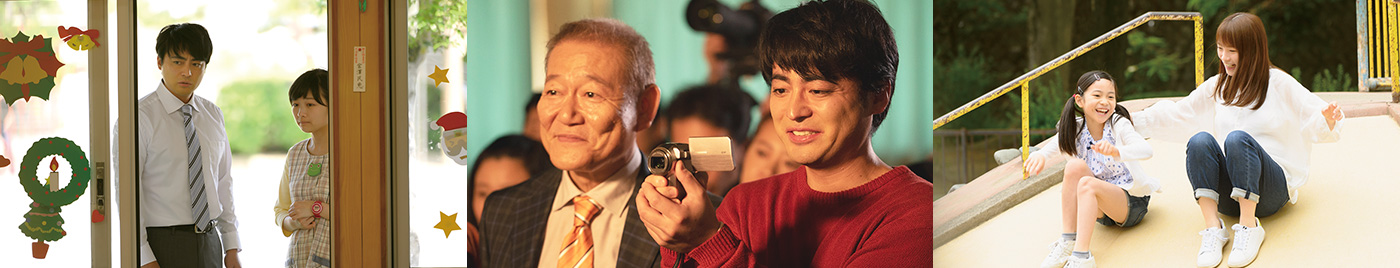



ソーシャルアップデート
もっと見る